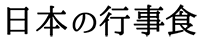おせちとは
おせち料理とは、正月に食べるお祝いの料理です。もともとは豊作を感謝し、神様へのお供えものとして作られていましたが、今では様々な縁起物や願いを込めたお料理が振る舞われています。
おせちの由来
元々は、元旦だけでなく五節句などの節日に豊作を感謝する儀式が執り行われており、その儀式で神様にお供えしたものを「節供(せちく)」と言いました。
奈良時代から平安時代の時期は宮中行事として節の儀式が行われ「御節供」が振舞われていましたが、江戸時代には「御節供」が庶民にも広まり、1年の節日で一番大切なお正月のお料理が「おせち料理」と呼ばれるようになったそうです。
お重の段ごとに入れるお料理
縁起を担ぎ「箱を重ねる=めでたさを重ねる」と言う意味から、お重が使われます。正式には五段重が用いられ、段ごとに入れるお料理が決まっています。五の重は、諸説ありますが将来この重をいっぱいにできるほど栄えるようにと空にしておくしきたりもあります。
一の重(祝い肴・口とり)

正月にふさわしい祝い肴を詰めます。
数の子、田作り、黒豆、紅白かまぼこ、伊達巻、昆布、栗きんとんなど
中でも、数の子・田作り・黒豆(関西ではたたきごぼう)を「三つ肴」といい、正月には欠かせないものとされています。
二の重(焼き物)

主に縁起のいい海の幸を詰めます。
ぶり、アワビ、タイ、エビなど
三の重(煮物)

山の幸のお煮しめを詰めます。
お煮しめ(レンコン、里芋、しいたけ、ごぼう、梅花にんじん)
与の重(酢の物・和え物)
主に酢の物を詰めます。
紅白なます コハダ粟漬け 菊花カブなど
※忌み数字の四は使わない
料理に込められた意味
一の重

黒豆
まめ(勤勉)に働き、まめ(健康)に暮らせるように
数の子
子宝に恵まれ、子孫繁栄するように(卵の数が多いから)
田作り
片口イワシを撒いて豊作となった田畑があったことから、五穀豊穣を願う。
紅白かまぼこ
日の出を表し、門出を祝う意味がある。紅は慶び(魔除け)、白は神聖(清浄)の意味を持つ。
昆布巻
「喜ぶ」にかけて縁起をかつぎ、健康長寿を願う。
伊達巻
巻物に似ていることから、知識が増えることを願う。
栗きんとん
黄金色をしていることから財宝にたとえられ、金運を呼ぶ。
ニの重

タイ
「めでたい」に通じる
アワビ
肉が伸びることから、永遠を表す
ブリ
出世魚であることから、立身出世ができるように願う
エビ
体が曲がり、ヒゲがある姿が老人に見えることから、長寿を願う
三の重

煮しめ
土の中で根を張る根菜が中心で、末永い幸せを願う。
レンコン
穴が空いていることから将来の見通しがきくように
サトイモ
小芋が多くつくことから、子孫繁栄を表す
ごぼう
根を深くはることから、家族が代々繁栄するように
しいたけ
神笠や亀の甲羅に見立て、健康で長生きできるように
梅花にんじん
梅は花が咲くと必ず実を結ぶことから、めでたいものとされ、色は寿を表す
与の重
菊花カブ
菊は邪気を払い、不老長寿の象徴とされる
紅白なます
紅白はめでたさを表、根菜のように根を深くはり、代々続くように
コハダ粟漬け
コハダはコノシロの稚魚で出世魚であり、縁起が良い。クチナシで黄色く染めた粟で、五穀豊穣を願う
その他の正月の行事食
雑煮

本来は大晦日に神に供えた餅や、にんじん、大根などの野菜を元旦に下げて若水で煮込み、神と人が一緒に食べた汁物を「雑煮」という。
正月に欠かせない行事食として根付いたのは室町時代の後期だと言われる。
具材や作り方、味漬けは地域により様々。
おおむね関東では角餅にすまし汁、関西では丸餅に味噌仕立てにする。
関東では、江戸時代に人が増えて一度にたくさん作る必要が生まれ「のしもち」を切って角餅にしたことから、関西では「角が立つのは縁起が悪い」として、具や餅を丸く仕立てたことから形に違いが生まれたとされている。
お屠蘇

「お屠蘇」は一年の邪気をはらい、延命長寿を願うために飲む薬酒。
「屠」には悪魔を屠る(葬る)、「蘇」には魂を蘇らせるという意味があり、正月には欠かせないものとされた。
本来は「屠蘇散(とそさん)」と言われる薬酒を調合した生薬を、日本酒かみりんに浸して作りますが、今では日本酒がお屠蘇に使われることがほとんどです。
若い生命力をもらうため、年少者から年長者へと順に飲むのが習わしです。
飲むときは「一人これ飲めば一家苦しみなく、一家これ飲めば一里病なし」と唱える。