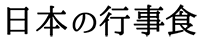新嘗祭とはその年の五穀の収穫を感謝し翌年の豊作を祈願する古くからの祭儀。現在の勤労感謝の日が、新嘗祭の日となります。
十三夜(じゅうさんや)とは、十五夜の後にめぐってくる十三夜(旧暦9月13日)のことを言います。一年で十五夜の次に美しい月を眺めることができます。
十三夜には栗や枝豆を供えることから「栗名月(くりめいげつ)」「豆名月(まめめいげつ)」とも呼ばれます。
かつて月見は十五夜(旧暦8月15日)と、十三夜(旧暦9月13日)に行われるものとされ、一方だけを見るのは「方月見」といって縁起が悪いとされていたようです。
せっかく1年で一番月が美しい十五夜を楽しんだら、合わせて十三夜を楽しむのもオツですね。
十三夜の行事食
月見団子
穀物の収穫に感謝し、米が原料である団子を月に見たてて丸めて作ったのが月見団子のはじまりです。
ご飯の団子をピラミッド状に高く積み上げるのは、団子の先端が「霊界」につながると信じられていたから。団子を通して、収穫の感謝の気持ちを月に伝えていました。
団子の数は地域により異なりますが、十五夜は15個、十三夜は13個とすることが多いようです。
栗・豆

十三夜は、栗や枝豆の収穫祝いでもあったため別名「栗名月」「豆名月」とも呼ばれます。
「栗」は秋の味覚の代表格。栗と日本人のつながりは古く、縄文時代にまでさかのぼり、古くは主食や救荒作物として食を支えてきました。
秋の味覚の代表である栗ご飯。ぜひ十三夜に味わいたいですね。