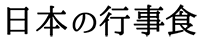新嘗祭とはその年の五穀の収穫を感謝し翌年の豊作を祈願する古くからの祭儀。現在の勤労感謝の日が、新嘗祭の日となります。
今でも皇室では新嘗祭は、宮中祭祀の中の最も重要なものとされています。天皇が神様に初穂をお供えし、それを神様とともに食しその年の収穫の感謝を捧げ、翌年の豊作を祈ります。
万葉集にも新嘗際にまつわる和歌が存在し、古くから日本に根付くこの行事。やっぱり日本人にとってはお米は特別な存在。
十月は日本中の神々が出雲大社に行くことから「神無月」と呼ばれています。ただ、その中でただ一人、出雲に行かずに地域を守るのが「恵比寿弁天」。恵比寿弁天は七福神の一人で、海上、漁業、商売の守り神です。
恵比寿講の日には市が開かれ、魚や青物、縁起物を飾った福笹や熊の手が売られます。関東では主に10月20日に行われ、農業の神とする傾向が強いので「二十日恵比寿」「百姓恵比寿」と言われ、関西では正月10日に行われ、商いの神とする傾向が強いので「十日戎(えびす)」「商人恵比寿」と言われています。
恵比寿講の行事食
タイ
恵比寿講では「行事食」とされるものはないのですが、恵比寿様にちなんで、恵比寿様が抱えている尾頭つきのタイがお供えによく使われます。尾も頭もすべてそろい最初から最後まで続くという意味があります。